京都観光 おすすめ 京都の芸術 茶道
京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 茶道 平安時代~鎌倉時代

茶が初めて中国から輸入されたのは平安時代初期ですが、喫茶の風習は一部の貴族や僧侶の間で広まるにとどまりました。喫茶が本格的に普及するのは、鎌倉時代の初期で、僧栄西が宋から臨済禅とともに茶種と喫茶法を伝えてからになります。寺院を中心に喫茶が広まり、京都の栂尾や宇治など各地で茶が生産され始めました。鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、本茶とされた栂尾の茶と他の産地の茶(非茶)を飲み分ける茶寄合(闘茶会)が武家や庶民の間流行しました。
京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 茶道 室町時代~江戸時代

茶礼と称する茶会の方式が定まるようになる室町時代末期には、村田珠光によって禅の精神をとりいれた草案の茶が創始されました。これを受け継いだ千利休が安土桃山時代に茶の湯を完成させました。その後江戸時代初期にかけて茶の湯は諸大名に好まれて全盛期を迎え、三千家などの茶道宗匠も大名のお抱えとなりました。茶道宗匠は京都で町人社会への茶の普及を図り、江戸時代中期には家元を中心とする段階的な免許制度により門人の組織化を進めました。江戸時代後期には、中国の文人趣味の影響をうけた煎茶が、京都の文人たちの間に流行し、煎茶の家元も誕生しました。
京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 茶道 三千家

千利休を祖とする茶道家元の三家は表千家・裏千家(ともに上京区小川通寺之内上)・武者小路千家(上京区武者小路通小川通東入)のことを言います。千利休の孫の千宗旦は千利休の侘茶の道を究め、千宗旦の三男の江岑宗左(こうしんそうさ)は表千家を、四男の仙叟宗室(せんそうそうしつ)は裏千家を、次男の一翁宗主(いちおうそうしゅ)は武者小路千家をそれぞれ興し、三千家が確立しました。
江岑宗左(こうしんそうさ)は紀州徳川家、仙叟宗室(せんそうそうしつ)は加賀前田家、一翁宗主(いちおうそうしゅ)は讃岐高松松平家に出仕して経済基盤を固めました。代表的茶室には、表千家の不審庵、裏千家の今日庵(重要文化財)、武者小路千家の官休庵などがあります。
京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 茶道 薮内家
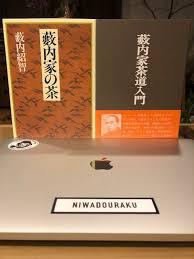
下京区西洞院通正面下にある茶道家元です。当主は代々紹智(じょうち)を襲名します。武野紹鴎門下で千利休の弟弟子にあたる剣仲紹智を初代として現在に至ります。代々西本願寺の保護を受けました。邸内には茶室燕庵があります。
京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 茶道 煎茶道

抹茶を用いる茶の湯に対して、茶葉を湯で煎じ出して飲む作法。中国の明・清の文人趣味の影響を受けて江戸時代後期に成立しました。京都に煎茶を普及させたのは黄檗僧売茶翁(高遊外)で東山に茶亭通仙亭を設けお茶を提供しました。その後小川可進が煎茶手前を創案して煎茶家元の先駆けとなり、公家や文人の間に煎茶道を流行させました。
関連する投稿
- 京都観光 おすすめポイント 京都の芸術 花街のしきたり Art Kyoto Hanamachi
- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 花街の行事 Art Kyoto Hanamachi
- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 花街の歴史② Art Kyoto Hanamachi
- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 花街の歴史① Art Kyoto Hanamachi
- 京都観光 おすすめ 京都の芸術 京舞と井上流 Kyoto Art Kyomai(Kyoto Dance)
現在の記事: 京都観光 おすすめ 京都の芸術 茶道






