京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京象嵌・京人形・京表具・京刃物
京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 京象嵌
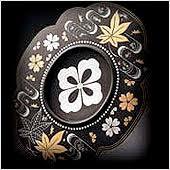
象嵌の技術はシルクロードを経由して日本に伝わりました。江戸時代には刀剣のつばなどに豪華な象嵌を施すのが流行しました。明治時代の廃刀令により京象嵌は大打撃を受けましたが、京都博覧会などでその技術が海外に宣伝され土産物として珍重されました。金属に金や銀や赤銅などをはめ込んで装飾するのが京象嵌の特徴です。ペンダント、帯留め、タイピン、高級バッジなどで知られています。地金に細かい布目の溝を掘り、金・銀・銅などをツチで打ち込む布目象嵌が中心で「目切り3年」といわれ地金に布目タガネを小さなカナズチでたたきながら、布目模様を入れます。肉眼ではほとんど見えないほど細い布目に金・銀・銅などを嵌め、酢洗い腐食、漆焼き、表面磨き、華麗な毛彫などの行程があります。
京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 京人形

古来人形は、天児(あまがつ)や這子(ほうこ)など子供の身代わりに悪いことを引き受けるものとして用いられていました。京都には嵯峨人形、賀茂人形、御所人形、伏見人形などがあります。現在では三月三日と五月五日の節句人形が中心です。京雛は、頭師、髪付け師、手足師、小道具師、胴着付け師などの分業で熟練の技が伝承されてきました。京都には周囲に仏具関係、繊維関係、漆芸関係などの工芸が発達していて人形作りの環境には適していました。
代々皇女が入寺した大聖寺、宝鏡寺、三時知恩寺、霊鑑寺などの尼門跡寺院には、江戸時代の優れた人形が今に伝わっています。拝領人形ともいわれ大名への贈答品となりました。
京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 京表具

表具の歴史は、仏教とともに伝来した経巻を仕立てることに始まります。やがて仏画などを礼拝用に制作するようになり、これが現在の表装のもとになりました。室町時代に茶道がさかんになると多数の書画が生まれ、形態や内容に応じた表装が施され、床の間などに飾られるようになりました。
掛け軸や巻物は、書画本体である本紙や布地の裏に糊で紙を貼って補強し、その各部分をつなぎ合わせた上でさらに全体を総裏打ちします。襖、屏風、衝立などは骨格の上に下張り、張り、上張りの順に糊で紙を貼り重ね、最後に外枠をはめ込みます。京都は裏打ちのための上質な和紙、裂地となる染織、良質な地下水に恵まれています。京都では掛け軸・額・屏風・襖絵などの担当を表具師と呼び、経典、和本などの担当は経師といわれいます。
京都観光 おすすめポイント 京都の工芸 京刃物

京刃物は、料理、宮大工、竹工芸、造園、仏像美術など多様な分野で京都の伝統を支えています。料理に使う包丁だけでも、出刃(でば)・柳刃(やなぎば)・菜切り・ハモの骨切りからマグロ切包丁まで色々な種類が存在します。京刃物はへいあんじだいの名刀工三条小鍛冶宗近の伝説などもあり数々の名工を輩出しました。これを支えたのは出雲地方の砂鉄、玉鋼(たまがね)と京都の鳴滝砥石、伏見の土、丹波の松炭などです。仕上げの砥石は特に大切です。
関連する投稿
- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京縫・京黒紋付染・京組紐
- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京小紋・京鹿の子絞り・西陣織・友禅染
- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京仏具・京印章・神祇装束調度品・京石工芸品
- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京竹工芸品・京扇子・京団扇
- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京焼・京漆器・京指物
現在の記事: 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京象嵌・京人形・京表具・京刃物






